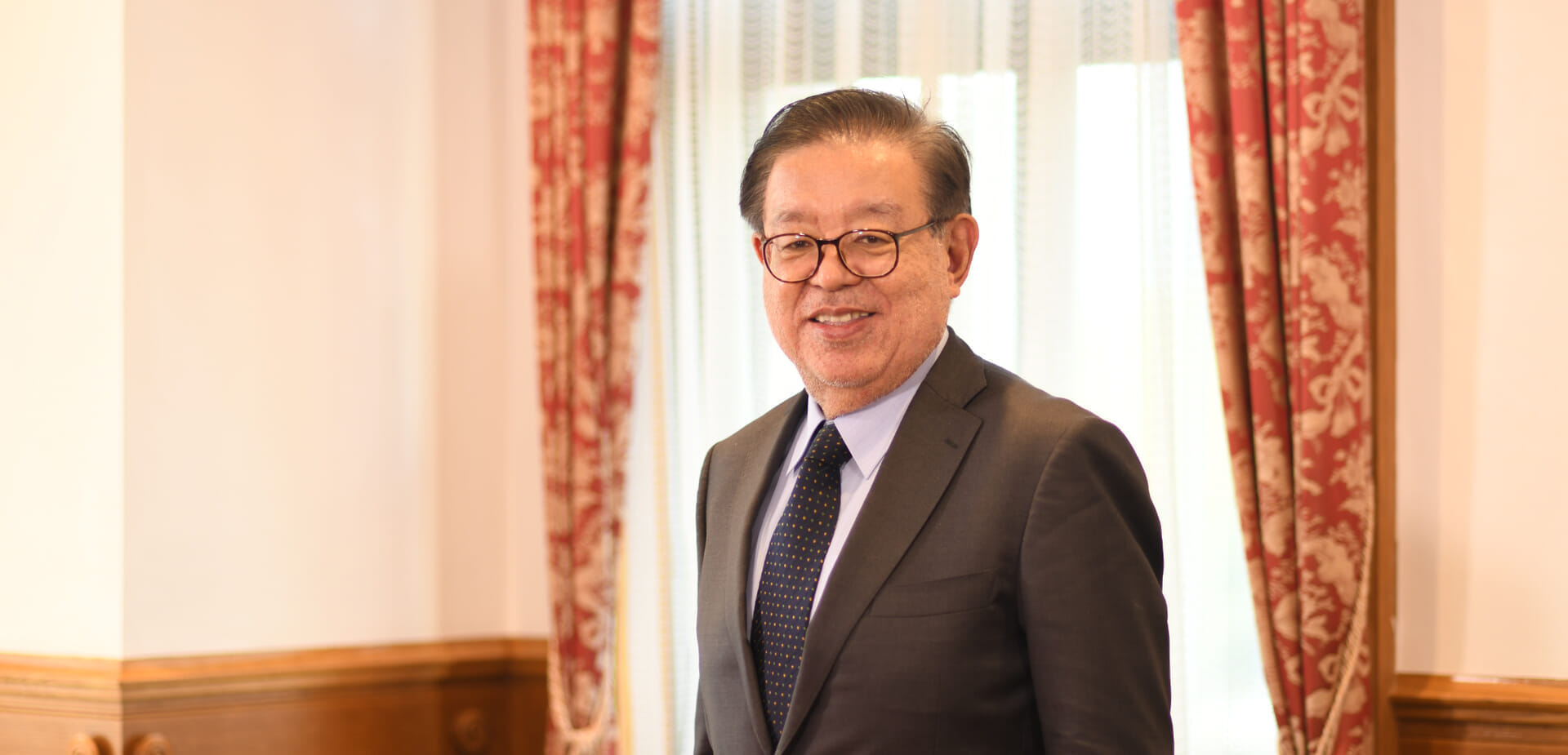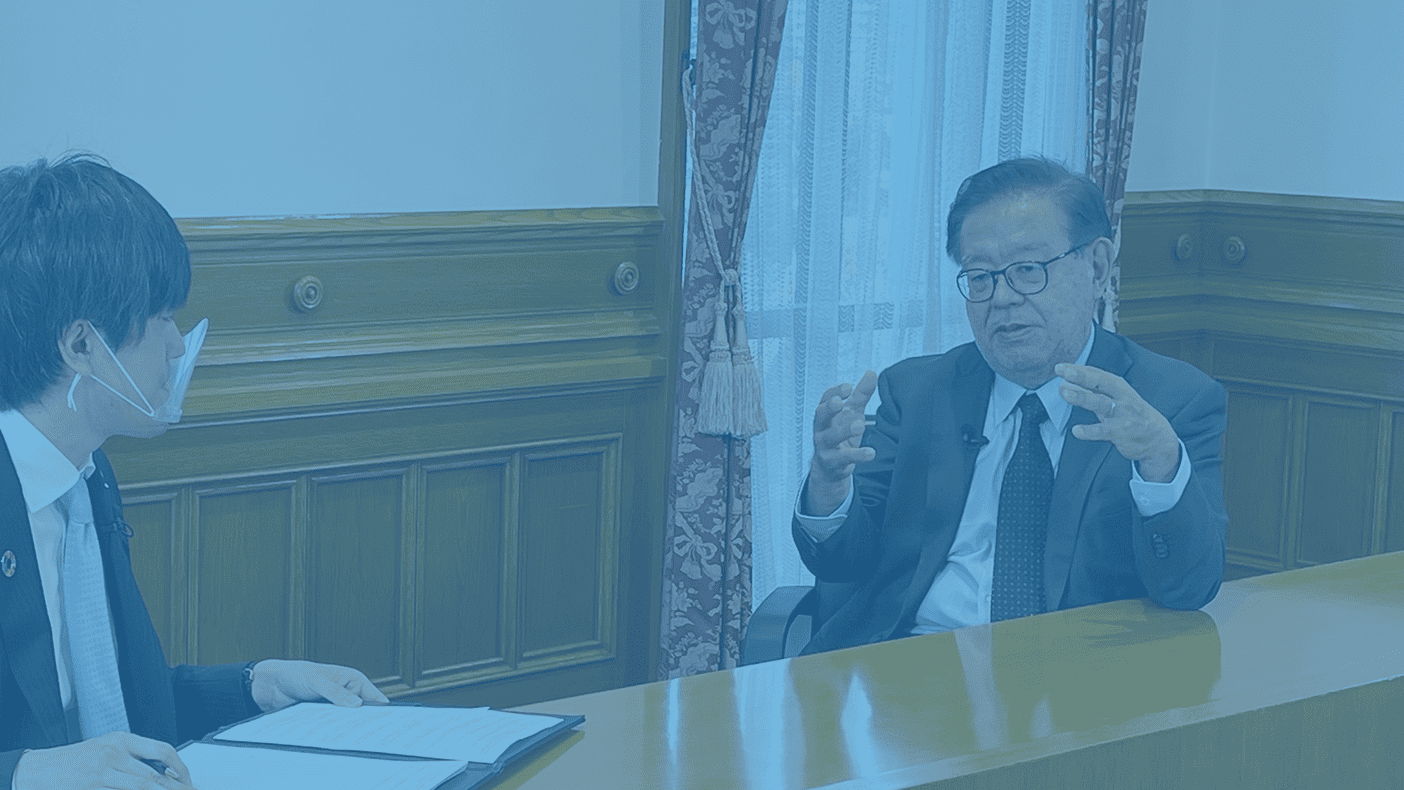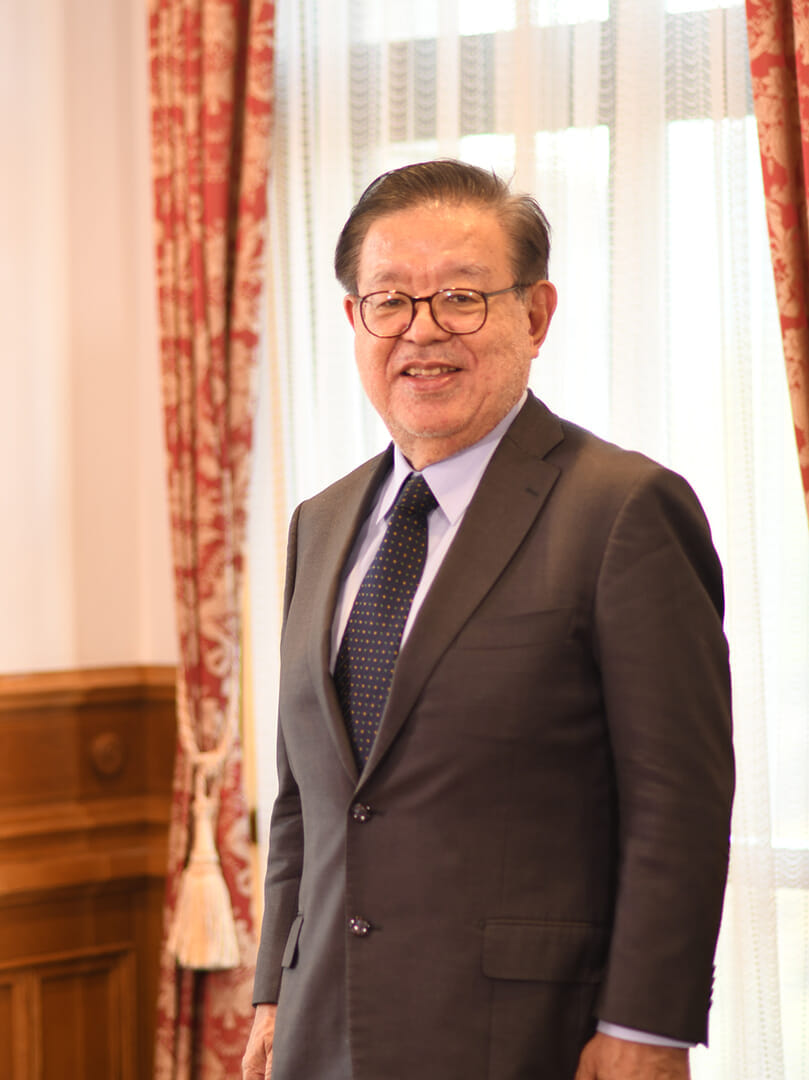インターネットは人間のために何ができるのか
テクノロジーのあるべき姿

村井教授がはじめてインターネットの構想を思い描いたのはいつ頃のことでしょうか?そのとき、どのような思いでしたか?
大学の学部時代にコンピュータを学び始めたときですね。そのときの大型コンピュータの使い方が気に入らなかったんです。コンピュータが真ん中にあって、人間がその周りで「計算してね」とお願いしているようなスタイルだったんです。やはりコンピュータは道具ですから、人間が真ん中にいて、コンピュータが周りにいて、人間のことを支えていくのが、道具としてのテクノロジーのあるべき姿だと私は考えていました。コンピュータを勉強するということが、人間がコンピュータに傅(かしず)いているように見えて、「これでは使い方が逆だろう」と思っていました。当時は、コンピュータ1台にそれぞれの人間が行くしかなかったんです。つまり、コンピュータがバラバラに人間を支えるなら、コンピュータ一つひとつが繋がっていないといけないですよね。だからコンピュータネットワークという発想になったんです。人間のためにコンピュータは何ができるのか、やはりそういうテクノロジーとしての期待がある、それが原点ですね。
育ての親ともいえる村井教授から見て、ご自身の子どもとしてのインターネットは、現在どのような姿に見えますか?インターネットは色に例えると何色でしょうか?その理由は何でしょうか?
そうですね、私たちはよくブルーの色を使います。地球全体を覆っているのがインターネットだとすると、やはり青い海や青い空といったイメージがあるからです。
インターネットの最大の特徴は、地球上のコンピュータを全部つなぐということです。ただ、これは意外と国が全部調節しているとできないことなんです。我々のように作っていく人間が、アカデミズムや教育などの目的で、何のバイアスも受けず、子供たちの教育をするとか、研究を進めるということは、グローバルに人類全体の共通の目的であると思います。そのためにコンピュータをつないでいくんだと、夢中になっていましたね。そういう意味では、育ってきたインターネットは、地球全体に満遍なく行き渡ったと、そろそろそのように表現してもいいと思います。インターネットですべての人をつなぐとか、地球をつなぐとか、そのあたりのゴール感がようやく見えてきたので、よく頑張ったなと思いますし、楽観的に捉えてもいます。
今のインターネットの思想設計は、コンピュータであるUNIXの思想を受け継ぎ、拡大したものであると村井教授の本から学ばせていただきました。「計算する」ではなく「人を助ける」という思想のことです。具体的にはどのような形でその思想がインターネットに受け継がれたのでしょうか?
受け継がれたというよりも、UNIXのオペレーティングシステムの考え方は、インターネットそのものだと思います。コンピュータ、ハードウェアがあって、その上に基盤のソフトウェア、オペレーティングシステム(OS)がある。そして、ハードウェアの上にソフトウェアを作ることができ、汎用のコンピュータはそのように作ることができます。ビフォーUNIX、つまりUNIX以前のコンピュータは、ハードウェアを作った人がハードウェアの能力を最大に引き出すために、オペレーティングシステムを作っていました。ところが、UNIXは全く逆の発想で、人間がコンピュータをどう使うかという観点から、OSはこうあるべきだと提示したうえで、そのOSがどのハードウェアの上でも使用できるようにしていました。いわば、インターオペラアビリティ、相互運用性を考えているんです。つまり、足もとのハードウェアの違いを吸収しながら、人間がコンピュータを使って何をするのかを考えて設計されたオペレーティングシステムなんですよ。したがって、足もとがバラバラでも同じ使い方ができるんですね。
今のインターネットを見てください。ブラウザを通じて、全然別のコンピュータでも、スマホでも、PCでも、テレビでも、サイネージでも、やはり同じ環境で使えるじゃないですか。だから人間から見て、社会から見て、こうあるべきだという思想から、いろんなハードウェアを全部使っていくんです。そもそも通信をみてください。無線であっても、有線であっても、光ファイバーであっても、衛星であっても、動きますよね。「足まわりは何でもいいけれど、人と環境に合わせた設計を作ろうよ」と考えられていますよね。この発想はまさにUNIXです。基本、インターネットはそのようにできています。インターネットである限り、足まわりは全部違うんですね。5Gのインターネットを使ってる人もいれば、光ファイバーでつなげているところもあれば、衛星で飛んでいっているところもあれば、海底ケーブルを使ってるところもある。しかし我々は、インターネットのつながり方を気にしてはいません。この発想、設計思想こそがUNIXなんですよ。だからやはり非常に大事な原点だと思います。
村井教授は英語中心だった初期のインターネットを多言語対応へと導きました。また、2019年には日本の文化である縦書きをWeb上で表現できるよう、国際的な標準化につなげてくださいました。しかし、どちらの例も「少数派だから使わなくても良いのでは?」という意見もあったと思います。そのような、判断や行動が迫られる場合に、村井教授が大切にされている考えや軸はどのようなものでしょうか?
おっしゃる通り、使う人がいなければ、標準化にしなくていいんじゃないかという議論は常にあります。しかし、「人間社会の基盤をコンピュータで作っていこう」といったときに、その多様性を尊重するのは、非常に大事なことなんです。例えばWebだと、言語の多様性がありますし、表現の多様性もあります。ビデオのストリーミングでも、非常に良い環境で視聴できるときは、綺麗な映像を見ることができますよね。しかし視聴できない環境にあるからといって何も見えないということでは困るだろうと思います。
様々な人の多様性、ダイバーシティ、インクルージョンといった概念は、今、社会全体に広がってきていますが、早くから使われていたコンピュータのインターフェースには、その点において問題がありました。最初のコンピュータは「全部英語で作ればいいや」という考えがあったんです。実際、コマンドやプログラミング言語の記述の基本は、全部英語です。しかし、それらを多言語化していくことを考えると、いろいろな意味が出てくるんです。特に日本が、この役割を担うことに意味があるんですよ。インターネットやコンピュータのユーザー数を考えると、非英語圏で最もユーザーが多いのは大体、日本です。だから日本が努力をすれば、世界がそれについてくる。そうすると、世界全体が恩恵を受ける。そのためには標準化が大事なんです。つまり、我々は日本語のために努力しますが、それはすなわち多言語のために使えるように標準化を決めることでもあるんです。これをやっておけば、どんな少数民族が少数の言語を使おうと思っても、同じ方法、同じ基盤が活かせる。だから、日本のためだけではないんです。言語に関してはそれで良かったと思います。
しかし、問題は縦書きですよね。縦書きは、左から右に書くという文字を出す方向性が、世界の言語の中でマジョリティーなわけです。それでも、縦書きは多分、なくなることはない文化だと思うんです。だから、これをデジタル化されたときもしっかりと用意しようと思いました。さらにアラビア語は、右から左ですからね。つまり、ある文章があったときに文字の方向性の概念を表示の中に入れることは、やはりいろいろな人の役に立つんですね。英語でも、縦書きすることがあるんですよ。何か狭いところにネオンサインのような表示を、英語で縦に流していくこともあるでしょう。そういうときに、どういうお作法で流した方が見やすいのか。縦書きや横書きには、それぞれ普遍的な魅力があると思います。ただ、そんなところに努力するのは日本人ぐらいしかいないだろうし、そういう観点から我々はアプローチをしています。我々がやったら、そこで恩恵を受ける人は世界中で必ず出てくると思います。まだ他の人が目をつけていなくて、自分たちだけが気がついてやることができるのは、楽しいですよね。非常にモチベートされているところを自分たちで解いていけて、それを他でも喜んでくれる人がいて、人の役に立つことができれば、つくる者にとっては喜びですよね。