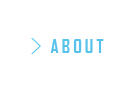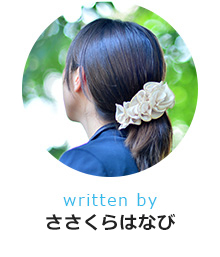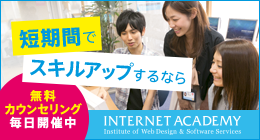震災被災者を救うインターネット
2016年9月 2日

医療とITの融合をテーマにした「インド人インターンの学生プロジェクト」という、ニシャンツ先生の記事の反響がよかったので、今回私の方では、日本での被災地支援をテーマにWeb技術の有効活用例をご紹介します。
東日本大震災では、Twitterが活躍
東日本大震災が起きた当時は、建物の倒壊などによってライフラインがストップし、生き延びるのに必要な情報もなかなか入ってこなかったそうです。
あそこで水が出た、と人づてに聞いても、実はそれは二日前の情報で、行ってみるともう水は止まっていたということもありました。
そこで人々が情報を探し求めたのがインターネットでした。 どこに避難できるか、どのような支援プロジェクトがあるのかといった有益な情報は、インターネットから入手しました。
特に、知人の安否確認などにTwitterが大活躍をし、ソーシャルメディアが情報伝達ツールとして一定の役割を果たしました。それを受けて、Twitter公式サイトでは、ヘルプセンターの中で、Twitterの活用方法として、安否確認や救助要請の仕方を紹介しています。
また、首相官邸でも「災害関連ツイッター」というものを用意しています。こういったサービスが、災害が起きたとき、実際に被害にあっている被災者にとって役立つといいですね。
気仙沼市が導入した災害情報システム
最近では、もう震災から5年以上経過しており、東日本大震災が話題にのぼることは少なくなってしまいましたが、福島のテレビでは、まだ放射線の線量を毎日伝えています。 そのような、まだ注意が必要な放射線情報や、災害時に役立つ情報などを集約した災害情報システムを、気仙沼市が市のWebサイトに導入しています。
災害時に限らず、テレビや新聞など大手メディアでは報道されないことも、インターネットでなら情報を入手できるということはまだまだ多くあります。 皆さんが新聞やテレビ、ひとつのWebサイトを見て疑問に思うことや、よく考えてみたらおかしいんじゃないかと思うようなことは、他のメディアで調べてみたら違う見解を発見するというのはよくあることです。 誰でも発信できるというWebのコンセプトがとてもポジティブに現れている例かもしれません。
ひとつのメディアに頼らず様々なメディアを参照することで、より正しい情報を得るということを日ごろから心がけたいですね。 また、Webの世界を構築していく側としても、幅広いユーザーに優しいWebコンテンツを作っていくというのは、常に心がけたいことです。
参考URL
本ブログは、日本初Web専門スクールのインターネット・アカデミーの講師が運営するWebメディアです。 スクールの情報はもちろん、最新のWebデザイン・プログラミング・Webマーケティングについて役立つ情報をご紹介しています。